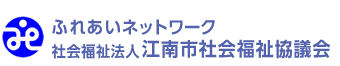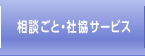門弟山小学校で「第1回ふくし交流会」を行いました 2013年6月28日
6月28日(金)の午後、門弟山小学校5年生の総合的な学習の時間で「第1回ふくし交流会」を行いました。
現在5年生は総合の時間で「福祉」をテーマに1年間かけて取り組んでいます。先日はユニバーサルデザイン学習の発表会を行いました。
今日は障がいのある方と「ふくし交流会」の授業を行いました。内容は1年間講師として交流する方との「出会い編」でした。講師としてくるみの里の方々、視覚障がい者の方、ろう者(聴覚障がい者」と手話通訳者の方々にお越しいただきました。
 くるみの里の利用者の方々は、自分の趣味のことで映画が好きだったり、パソコンが得意だったりといった内容を子ども達に伝えました。一番盛り上がったのは「恋愛トーク」でした(笑)。
くるみの里の利用者の方々は、自分の趣味のことで映画が好きだったり、パソコンが得意だったりといった内容を子ども達に伝えました。一番盛り上がったのは「恋愛トーク」でした(笑)。
 視覚障がい者のSさんはお話が上手なので、「自分は目が見えないけど、太陽が出ているか、わかると思う?」「月が出ているか、わかると思う?」といったように、子ども達とやり取りをしながらお話をしました。
視覚障がい者のSさんはお話が上手なので、「自分は目が見えないけど、太陽が出ているか、わかると思う?」「月が出ているか、わかると思う?」といったように、子ども達とやり取りをしながらお話をしました。
 ろう者のTさんは、旅行で鹿児島に行ったことや、手話サークルでの思い出をお話いただきました。子ども達からは手話を教えてほしいと要望があり、一生懸命覚えて、すぐに実践していました。
ろう者のTさんは、旅行で鹿児島に行ったことや、手話サークルでの思い出をお話いただきました。子ども達からは手話を教えてほしいと要望があり、一生懸命覚えて、すぐに実践していました。
 同じくろう者のWさんも趣味のことや好きな芸能人とかお話をし、マンガの「ワンピース」のことで子ども達と盛り上がりました。最後に手話を教えたり、子ども達が積極的に手話を覚えてくれようとしてくれたことにとても感激していました。
同じくろう者のWさんも趣味のことや好きな芸能人とかお話をし、マンガの「ワンピース」のことで子ども達と盛り上がりました。最後に手話を教えたり、子ども達が積極的に手話を覚えてくれようとしてくれたことにとても感激していました。
現在、ふくし交流会は門弟山小学校、布袋小学校、布袋北小学校の3校が取り組んでいますが、子ども達が積極的に交流をしながら、いろんなことを学んでくれる姿を見て、これからがとても楽しみです。(M.I)
愛知県社会福祉協議会の会議に出席しました 2013年6月26日
6月26日(水)の午後、愛知県社会福祉協議会にて2つの会議に出席しました。
始めの会議は、東海北陸ブロック社協職員を対象にした研修会の実行委員会でした。9月に東海北陸ブロック(愛知県・名古屋市、岐阜県、三重県、石川県・福井県・富山県)の社協職員が集まり、分科会を中心とした研修会が愛知県の蒲郡市で開催されますが、実行委員として参画しています。
 会議の途中から各分科会の企画担当に分かれ、内容を話し合いました。
会議の途中から各分科会の企画担当に分かれ、内容を話し合いました。
9月に開催予定ですが、準備期間はあまりないので急ピッチで進めていくことになります。
2つ目の会議は、愛知県社協ボランティアセンター福祉教育推進部会に出席しました。
愛知県社協では、今年度「ボランティア・市民活動推進計画」を策定予定ですが、内容については部会で話し合った内容を掲載していくとのこと。
 会議の始めは、ボランティア・市民活動推進部会と福祉教育推進部会の合同会議でした。この会議で「ボランティア・福祉教育推進計画」を策定することについて話し合いを行いました。
会議の始めは、ボランティア・市民活動推進部会と福祉教育推進部会の合同会議でした。この会議で「ボランティア・福祉教育推進計画」を策定することについて話し合いを行いました。
 会議の途中から各部会に分かれて話し合いを行いました。福祉教育に想いのあるメンバーなので中身の濃い話し合いができました。
会議の途中から各部会に分かれて話し合いを行いました。福祉教育に想いのあるメンバーなので中身の濃い話し合いができました。
2つの会議が続くと大変ですが、中身の濃い話し合いができるとほどよい疲れになります。地元だけでなく他の地域がどんな取り組みをしているのかを知るだけでもモチベーションにつながります。(M.I)
門弟山小のユニバーサルデザイン学習発表会に参加しました 2013年6月25日
6月25日(火)の午後、門弟山小学校5年生が総合の時間で取り組んでいる「ユニバーサルデザイン学習発表会」に参加しました。
門弟山小学校5年生では、総合の時間で1年間「福祉」に取り組んでおり、江南市社協では学習のサポートをしています。
5月に「ふくしってな~に?」をテーマにユニバーサルデザイン学習の授業を行いました。その後、アピタ江南西店へ行き、店内のユニバーサルデザインを見つけにいったり、ゴールデンウィーク中に家族に生活の中で困っていることやいろんな工夫があったらいいなということを聞いたりして「市場リサーチ」をしました。
今日は市場リサーチした後に、子ども達自身が「ユニバーサルデザイン」を考え、形になったら良いものを発表し、社協職員がコメントをする発表会を行いました。
1クラス3グループ分かれて考えたユニバーサルデザインを発表してくれましたが、①車に着目した「季節センサー」、②ラップを簡単に外せる「ラクラップ」、③自動的にちぎれたり、色で長さが分かる「エコにやさしいトイレットペーパ」、④約束時間に必ず教えてくれる「約束時間お知らせモニター」、⑤誰にでも簡単に使える携帯電話・スマートフォン「S・Kちゃん」、⑥めざまし時計の機能とパン焼き機を組み合わせた「目覚まし付きパン焼き機」。
どれも思いつきではなく、今まで学んだこと、市場リサーチしたこと、みんなでアイデアを出し合って形にしていくプロセスがわかって、とても良い学びの時間でした。授業ではなく、企業の商品開発のプレゼンテーションかと思うほど、アイドマの法則(注意・関心・欲求・記憶・行動)の要素も含みながら、自分もこんな商品があったら欲しいと思いました。
金曜日は「ふくし交流会」として障がいのある方との交流会が始まります。子ども達は「ふくし」を学ぶこと、交流していくことをとても楽しみにしてくれています。どんな出会いが待っているのか、今から本当に楽しみです。(M.I)
布袋小学校で「第1回ふくし交流会」を行いました 2013年6月24日
6月24日(月)の午前、布袋小学校5年生の総合的な学習の時間で「第1回ふくし交流会」を行いました。
今年度から布袋小学校の4年生では、総合の時間で1年間を通して障がいのある方と「ふくし交流会」の授業を行うことになりました。なぜかというと、昨年度に布袋北小学校で実際に取り組んでいただいた先生から、布袋小学校の先生に「ふくし交流会」の取り組みの素晴らしさを伝えていただいたことがきっかけでした。
今日は第1回ということで、1年間講師として交流する方との「出会い編」でした。といっても講師の自己紹介を子ども達に聞いてもらって「どんな人なのかな」を知る授業を行いました。
 視覚障がいのSさんは、事前に自己紹介の原稿を自分で点訳したものを持参いただきました。子ども達はSさんが指で点字を触りながら原稿を読んでいく姿に釘付けでした。
視覚障がいのSさんは、事前に自己紹介の原稿を自分で点訳したものを持参いただきました。子ども達はSさんが指で点字を触りながら原稿を読んでいく姿に釘付けでした。
 難聴者のFさんは要約筆記サークル藤の方のサポートを受けながら、自己紹介を行いました。裁縫が得意なこと、NHKの「あまちゃん」のことなどをお話しましたが、子ども達からの質問も口の動きをみながら理解し、やりとりをしてくださいました。
難聴者のFさんは要約筆記サークル藤の方のサポートを受けながら、自己紹介を行いました。裁縫が得意なこと、NHKの「あまちゃん」のことなどをお話しましたが、子ども達からの質問も口の動きをみながら理解し、やりとりをしてくださいました。
 くるみの里のSさんは職員のSさんと一緒に自己紹介をしました。昨年度に布袋北小学校で講師として関わっていただいたので、子ども達とのやり取りも楽しくされて、嵐の話題やハワイのホノルルマラソンに参加したことをお話していただきました。
くるみの里のSさんは職員のSさんと一緒に自己紹介をしました。昨年度に布袋北小学校で講師として関わっていただいたので、子ども達とのやり取りも楽しくされて、嵐の話題やハワイのホノルルマラソンに参加したことをお話していただきました。
 子ども達も最初は緊張していましたが、時間が経つにつれ講師の方に自分からお話をしたり、とても雰囲気が良かったです。
子ども達も最初は緊張していましたが、時間が経つにつれ講師の方に自分からお話をしたり、とても雰囲気が良かったです。
次回は7月に行います。2学期・3学期と同じ講師の方と交流をしていくことになるので、子ども達から自己紹介をする授業になります。講師の方々も子ども達のことを知っていただき、素敵な1年間になればと思います。(M.I)
認知症キャラバンメイトの定例会に参加しました 2013年6月21日
6月21日(金)の午後、第2ジョイフル江南で「認知症キャラバンメイト定例会」に参加しました。
認知症キャラバンメイトとは、一般市民・団体を対象に「認知症サポーター養成講座」を実施していますが、その講師役のことを言います。
江南市の認知症キャラバンメイトは研修修了者が集まり、2か月に1回の定例会を行っています。
 今日は前回の定例会後から行った認知症サポーター養成講座の活動報告や25年度の定例会で行う活動内容について、具体的な取り組みについて話し合いを行いました。
今日は前回の定例会後から行った認知症サポーター養成講座の活動報告や25年度の定例会で行う活動内容について、具体的な取り組みについて話し合いを行いました。
他市町が取り組みを視察に行ったり、市内のグループホームにお邪魔し認知症の方々と交流したり、実際に介護をされている家族向けのサポーター講座を実施したりと、25年度の活動もてんこ盛りです。
この地道な活動を続けていくことで、認知症や家族の方々が安心して暮らすことのできる江南市につながっていければと思っています。(M.I)
ふくし交流会の打ち合わせを行いました 2013年6月20日
6月20日(木)の夜、老人福祉センターで「ふくし交流会」のろう者・手話通訳者の方々打ち合わせを行いました。
昨日、布袋北小学校で「ふくし交流会」を行いましたが、今年度は「ふくし交流会」の取り組みが門弟山小学校、布袋小学校に広がり、障がいのある方々がどの学校の子ども達と交流会を行っていくかを調整し、ろう者の方々には門弟山小学校5年生と交流していただくことになりました。
 今日は、内容と当日の流れを確認しました。昨年度に布袋北小学校で「ふくし交流会」にご協力いただいた方々でしたので打合せも昨年よりスムーズに行うことができました。
今日は、内容と当日の流れを確認しました。昨年度に布袋北小学校で「ふくし交流会」にご協力いただいた方々でしたので打合せも昨年よりスムーズに行うことができました。
実践と経験を積み重ねていただいたことで、ろう者の方々も「ふくし交流会」の目的をご理解いただいたと思っています。
蒸し暑い中、夜遅くまでご参加いただき本当にありがとうございました。本番もよろしくお願いします。(M.I)
布袋北小学校で「第1回ふくし交流会」を行いました 2013年6月19日
6月19日(水)の午前、布袋北小学校5年生の総合的な学習の時間で「第1回ふくし交流会」を行いました。
昨年度から布袋北小学校の5年生では、総合の時間で1年間を通して障がいのある方と「ふくし交流会」の授業を行うようになりました。
今日は第1回ということで、1年間講師として交流する方との「出会い編」でした。といっても講師の自己紹介を子ども達に聞いてもらって「どんな人なのかな」を知る授業を行いました。
「障がい」だけを見るのではなく、講師の「人」として出会ってもらうことが目的でした。
 視覚障がいの方は昨年度もふくし交流会の講師としてご協力いただきました。お仕事の話や趣味の話、目が見えないことは自分の特徴のひとつということを子ども達にお話いただきました。
視覚障がいの方は昨年度もふくし交流会の講師としてご協力いただきました。お仕事の話や趣味の話、目が見えないことは自分の特徴のひとつということを子ども達にお話いただきました。
 くるみの里の利用者の方と職員の方にお越ししただきました。利用者のKさんは「嵐」がとっても大好きな方で、子ども達と嵐の話題で気分も乗ってきて歌ったり踊ったり、ジャンプするほど楽しく過ごすことができました。
くるみの里の利用者の方と職員の方にお越ししただきました。利用者のKさんは「嵐」がとっても大好きな方で、子ども達と嵐の話題で気分も乗ってきて歌ったり踊ったり、ジャンプするほど楽しく過ごすことができました。
今日からが、ふくし交流会のスタートです。これから講師の方と子ども達がどのように交流していくか、とっても楽しみです。(M.I)
ハートフレンズ運営委員会に参加しました 2013年6月18日
6月18日(火)の午後、江南保健所にて「ハートフレンズ運営委員会」に参加しました。
ハートフレンズは精神障がいの方々の地域の居場所(フリースペース)ということで毎週金曜日の正午から午後3時まで愛栄ふれあいプラザで開催しています。
 今日は毎月1回に関係者が集まるハートフレンズ運営委員会がありました。この1か月の参加人数等の開催状況の確認や検討事項を話し合いました。
今日は毎月1回に関係者が集まるハートフレンズ運営委員会がありました。この1か月の参加人数等の開催状況の確認や検討事項を話し合いました。
話し合いの中で、ハートフレンズが変わらずにみんなで運営していくこと、続けていくことの大変さ・大切さを改めて共有することができました。
そして、問題を起こす人は「困った人」ではなく、方法がわからなくて「困っている人」ということも、事例を話し合う中で学ぶことができました。「ふり返り」をすることって、改めて大事なことだと感じた一日でした。(M.I)
ふくし交流会の打ち合わせを行いました 2013年6月17日
6月17日(月)、今日は小学校の「総合」の授業で行う「ふくし交流会」の講師の方々と打ち合わせを行いました。
午前は、視覚障がいの方とご自宅近くのカフェでご夫婦と一緒に打ち合わせを行いました。
子ども達に自己紹介をしながら、いろいろなことを話していただくのですが、内容をご理解いただき、話す内容もこれから自分で点字にして準備していただけることになりました。
午後からはくるみの里に行って、講師となる利用者や職員の方と打ち合わせを行いました。
 Sさんは昨年もふくし交流会に協力いただいたので事前に講師プロフィールも作成いただき、スムーズに打ち合わせもできました。パソコンが得意なのですが、日頃のお仕事についても知ることができました。
Sさんは昨年もふくし交流会に協力いただいたので事前に講師プロフィールも作成いただき、スムーズに打ち合わせもできました。パソコンが得意なのですが、日頃のお仕事についても知ることができました。
 今年度、新たに講師をお願いしたKさんも、子ども達との交流をすごく楽しみにしているとのことで、本当にありがたいです。
今年度、新たに講師をお願いしたKさんも、子ども達との交流をすごく楽しみにしているとのことで、本当にありがたいです。
 Sさんも今年度から協力いただきます。講師プロフィールを事前に作成するのですが、仕事のこと、趣味や特技のこと、人生で印象に残っていること、などなど取材と言う形で教えていただきました。
Sさんも今年度から協力いただきます。講師プロフィールを事前に作成するのですが、仕事のこと、趣味や特技のこと、人生で印象に残っていること、などなど取材と言う形で教えていただきました。
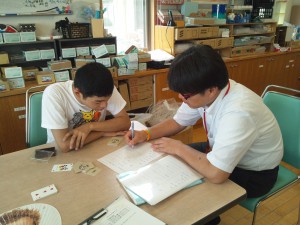 最後に水族館から帰ってきたばかりのAさんに同じように講師プロフィールの作成にご協力いただきました。子ども達もびっくりするような特技を持っていました。
最後に水族館から帰ってきたばかりのAさんに同じように講師プロフィールの作成にご協力いただきました。子ども達もびっくりするような特技を持っていました。
くるみの里はいつ行っても、温かく迎え入れてくれます。この明るさが施設の力の源なのかもしれませんね。ふくし交流会ではお世話になります。よろしくお願いします。(M.I)
愛知県社会福祉協議会の研修に参加しました 2013年6月14日
6月14日(金)、愛知県社会福祉協議会にて、「平成25年度地域福祉計画・地域福祉活動計画等策定推進会議」に参加しました。
研修内容は、地域福祉推進のために行政が策定する「地域福祉計画」と、社協が策定する「地域福祉活動計画」があり、計画を策定する意義や策定後の進行管理のためにどうしていくかといった内容でした。
 午前中は、岩倉市と小牧市の行政職員、社協職員より報告をいただき、その後日本福祉大学の学長補佐である原田正樹先生が報告を受けてのポイントをまとめたり、報告者に質問をしました。
午前中は、岩倉市と小牧市の行政職員、社協職員より報告をいただき、その後日本福祉大学の学長補佐である原田正樹先生が報告を受けてのポイントをまとめたり、報告者に質問をしました。
 午後からは基調説明として、原田正樹先生より「地域福祉計画・活動計画の策定、進行管理上の留意点」をテーマにお話をいただきました。その後分科会に分かれ、参加者同士で意見交換を行いました。
午後からは基調説明として、原田正樹先生より「地域福祉計画・活動計画の策定、進行管理上の留意点」をテーマにお話をいただきました。その後分科会に分かれ、参加者同士で意見交換を行いました。
地域福祉を推進していくためには、行政だけ、社協だけ、住民だけ、専門職だけ頑張るのではなく、より連携を深めていくことが大事であり、そのための「計画」をどう策定し、進行管理を行っていくのかがいかに必要かということを学ぶことができた研修でした。(M.I)